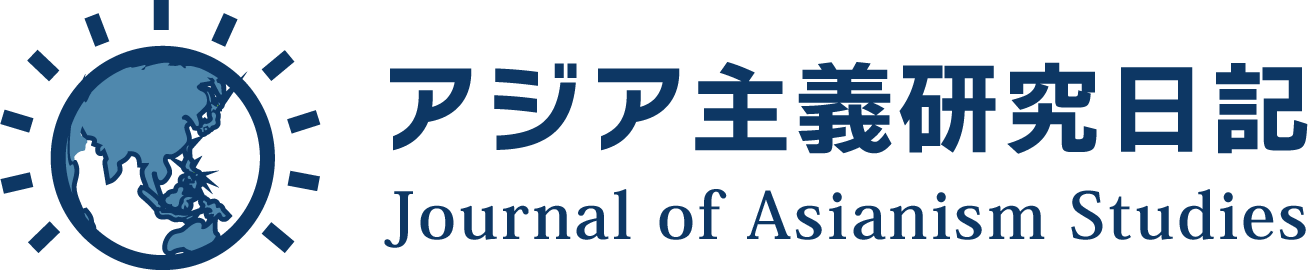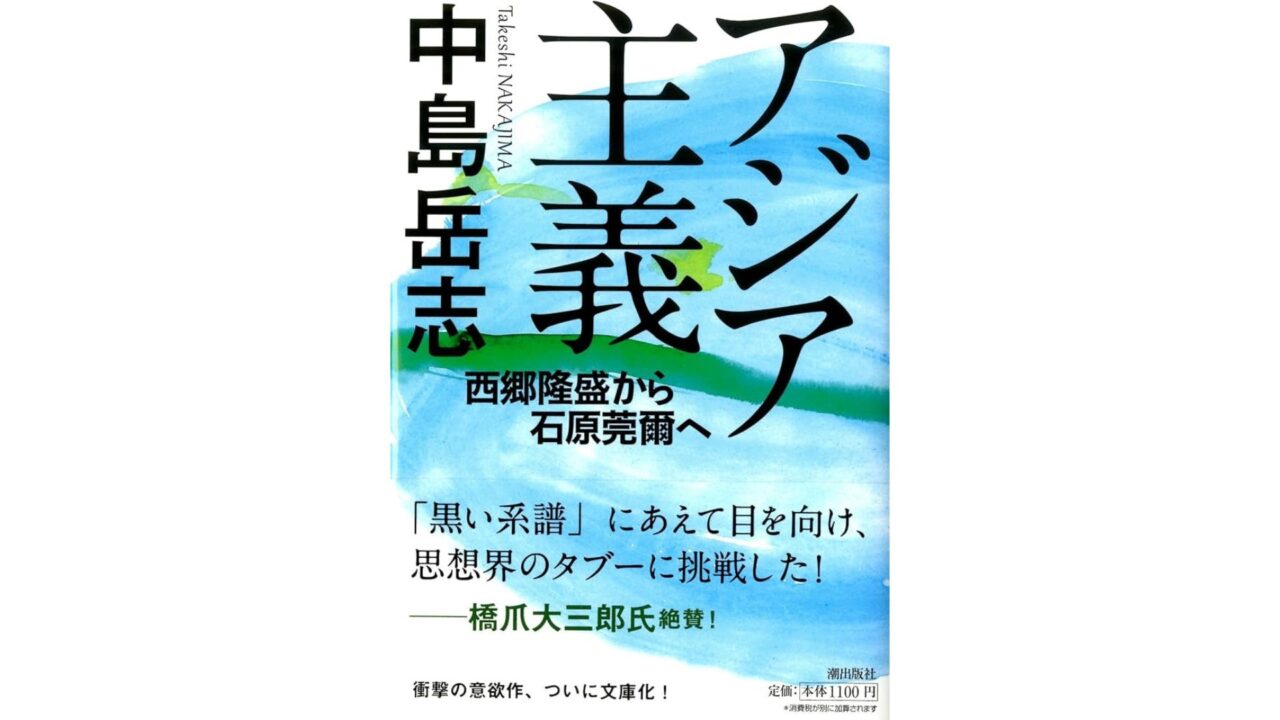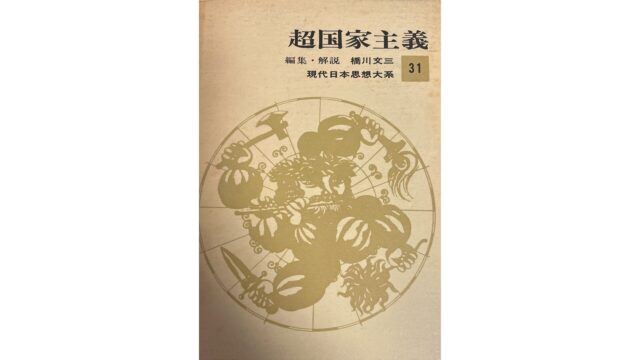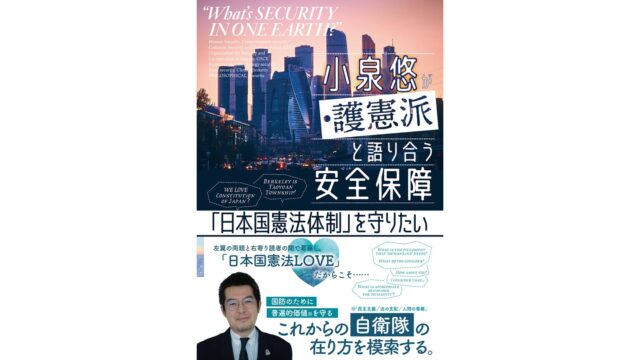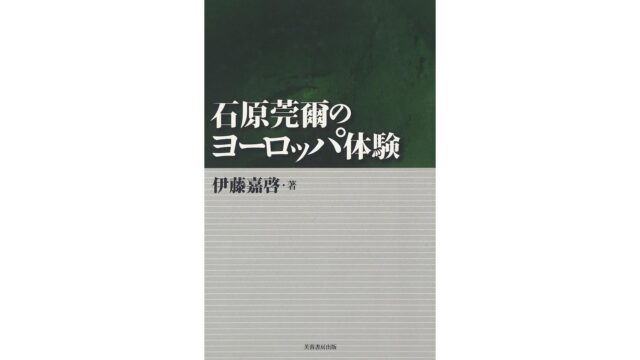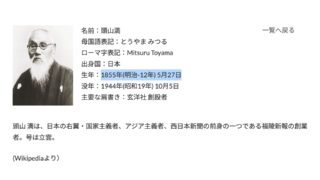近代化イコール西洋化??アジア主義者たちの奮闘と苦悩に思わず感情移入すること間違いなしの一冊。
思想家・岡倉天心は「Asia in One(アジアはひとつ)」といって、アジアに住まう人々に共通する思想「不二一元」を指摘し、アジア的価値の確立を主張した。これを拡大解釈し、「アジアはひとつ。だから我々が統一しますね。」と言ってしまうと不穏な空気が流れ始める。
ときは明治時代。西洋主導の近代化が進む中で、欧米諸国のアジア進出、植民地化に対抗する思想としてアジア主義は生まれた。アジア的な価値観の確立をめざしたこの思想は、いかにして「侵略主義」へと変容していったのか。
本書は、明治維新以降に生まれたアジア主義がたどった思想の変遷を、歴史の流れとともに紐解く本である。
アジア主義の3類型
そもそも、どこからどこまでがアジアなのか。世界地図を見ると、西はトルコ、東は日本までがアジアである。だがトルコは定期的にEUに入りたがっているし、サッカーW杯の予選ではオーストラリアなどのオセアニア地域がアジアに含まれている。
著者は、哲学者・三木清の思想を引用し、多種多様な文化を持つアジアに共通するものは「無の思想」であると主張する。この思想が通底する範囲がアジアで、アジア主義者がまなざす連帯の対象と定義された。
だが、この論理は前述の通り、侵略主義へと転化する危険をはらむ。ではアジア主義はすべて危険な論理なのか。そこで著者は、アジア主義の3類型を提案する。
①政略としてのアジア主義
ロシアとの緩衝帯として満州・朝鮮を勢力圏におくなど、政治的な思惑として、アジア主義を利用する考え方がこれにあたる。いわば、要注意なアジア主義である。
②抵抗としてのアジア主義
欧州の植民地支配からの解放、封建的な王朝からの解放など、カウンターアクションとしてのアジア主義。合言葉は「アジアの解放」だ。
③思想としてのアジア主義
アジアをひとつの共同体としてとらえ、思想的な意味を考える試みが、思想としてのアジア主義である。そこには岡倉天心が提唱した「不二一元」もあるし、京都学派のいう「近代の超克」もここにあてはまるだろう。
この本では②と③が主に取り上げられ、教科書ではほとんど名前を聞かない活動家や思想家が多数登場する。
「東洋の王道」と「西洋の覇道」
徳や仁義にもとづいて国をおさめる政治のやり方を「王道」、武力をもって支配しようとするやり方を「覇道」という。もともとは中国の儒教の考え方だったが、アジア主義者たちは、日本による外国への干渉を王道と呼んで支持する一方、西洋の強権的な植民地主義を、覇道として批判していた。
干渉というと聞こえが悪いが、本書に出てくる時代の日本人 ー前述の3類型の①②抵抗&思想としてのアジア主義者たちー は、アジア各国の活動家たちへの支援を惜しまなかった。
例えば福澤諭吉。「脱亜論」で展開された「我れは心に於て亜細亜東方の悪友を謝絶するものなり(訳:東アジアの奴らとはもう関わりたくない)」という激烈な文句が印象にのこる福澤だが、彼も元々は朝鮮の開化派・金玉均(キム・オッキュン)らの思想に共鳴し、日中朝の同盟を目指し支援を行った人物だった。
そんな福澤がいかにして脱亜論を執筆するに至ったか、詳細は本を呼んでいただければと思うが、朝鮮人を支援した福澤がとくに珍しいわけではない。この時代、他国との同盟や連邦を目指すアジア主義者たちはたくさん存在した。
父として導く?日本人の上から目線
日本・中国・朝鮮の合邦を主張した樽井藤吉の大東合邦論、国・民族を超えた東アジアの共同体を主張した三木清の東亜協同体論。そして日本・中国・満州の連盟結成を提唱した石原莞爾の東亜連盟構想と、当時の日本人にとって、中国・朝鮮(韓国)の心理的距離感は今では考えられないくらい近かった。
その根底にあったのは、民族や政府の垣根をこえて、インターナショナルな共同体を作っていこうという思想としてのアジア主義である。
彼らはあくまで、対等な立場として諸外国をみようとしていた。とはいえ、先に近代化した国として、また支援者として、日本のアジア主義者には多かれ少なかれ、日本が父であり盟主であるという意識はあったはずだ。それは孫文ら革命家を熱心に支援していた頭山満が満州をみて呟いた「だいぶ広いねえ。これは日本が取ってやらにゃ」という言葉にも表れている。
アジア主義の歴史から学ぶ
この本は、あくまで思想史であり、国家運営の決定権を持たないアジア主義者の考え(※)がそのまま歴史の出来事に反映されたわけではない。国家間の外交や当時の経済、安全保障状況にはほとんど触れられていないが、アジアの外にはアメリカがいて、ロシアがいて、日本には複雑な舵取りが求められていたことは確かだ。
ただ、どこか上から目線の「思想としてのアジア主義」が「政略としてのアジア主義」に結びついた先には、朝鮮併合や満州国の建国があった。その顛末は、こんにちまで東アジアの人々が日本に抱く複雑な感情を見ればわかるというものだろう。
戦前のアジア主義が侵略主義の象徴として「右翼思想」の文脈で語られることが多い一方、現代のSNSで中国や韓国に対する罵詈雑言を繰り広げる人たちは「ネット右翼(右翼)」と呼ばれている。熱心にアジアの国々を支援していた当時の右翼と現代のネトウヨでずいぶん解釈が違うものだと思うが、自分が持つ思想がいったいどこから来てどのように繋がっているものなのか、歴史を紐解いてみることは大切かもしれない。
著者は最後の章で、いわゆるネトウヨ的な歴史修正主義に警鐘を鳴らしている。と同時に歴史の過程によって構築されたアジア主義を評価し、「歴史によって分裂するのではなく、連帯を模索すること」を提案している。
大切なのは過去を正しく知り、正しく反省すること。歴史をじっくり見つめ、よりよい未来の形を志向する時、アジア主義は現代によみがえる。
※国家運営の決定権を持たないアジア主義者の考え…唯一の例外は関東軍に所属していた石原莞爾くらいだが、彼の場合は宗教的な思想も入ってくるのでなおさら複雑だ。正直この本の中で最も難解な章だった。