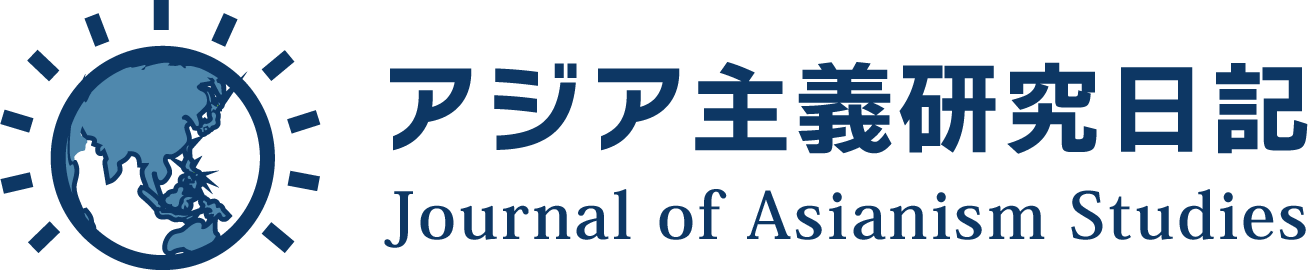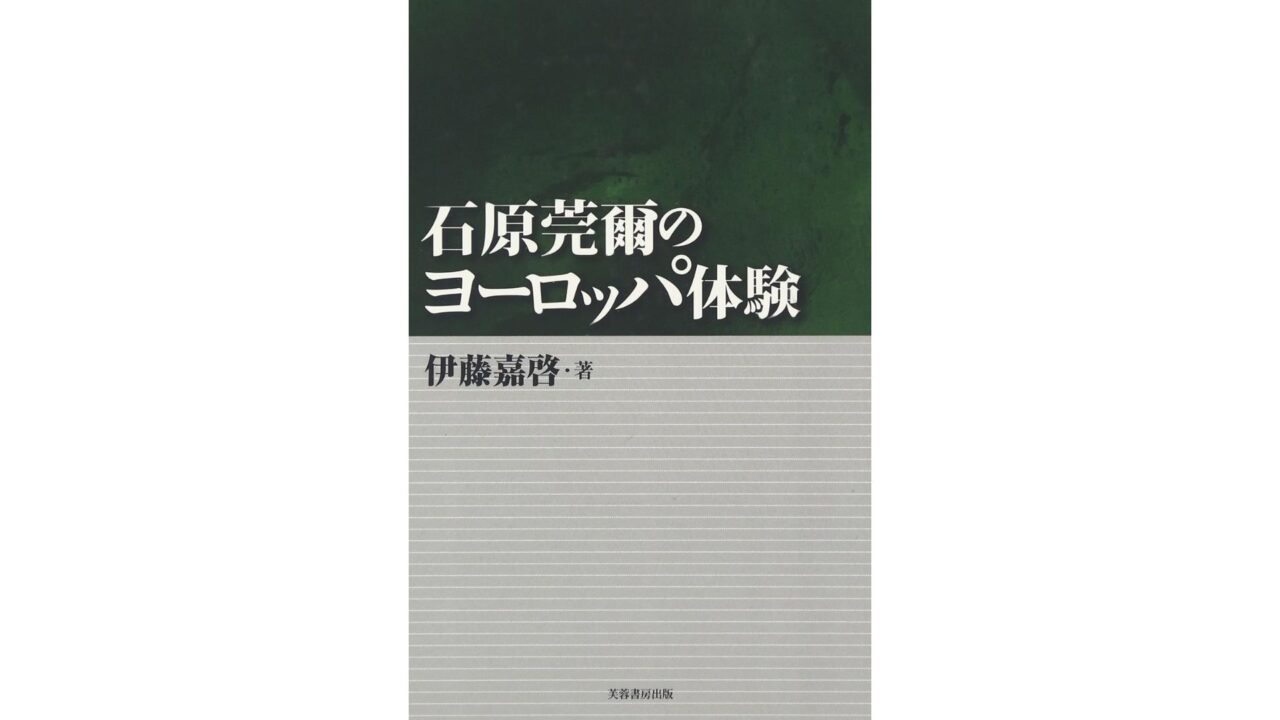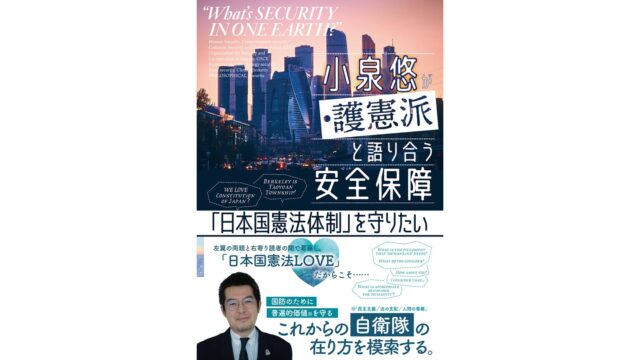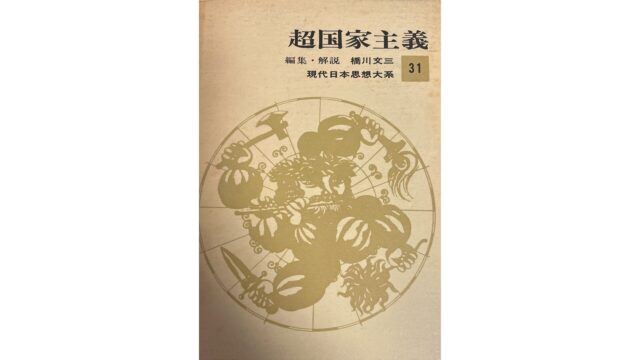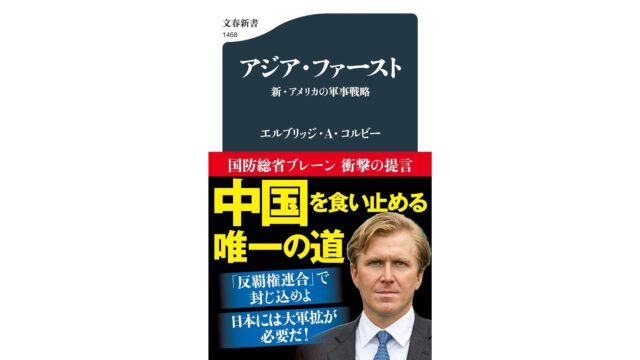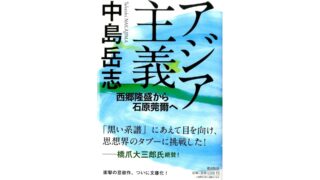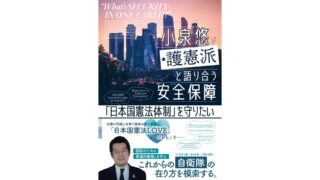自分のラブレターが100年後に出版されたらどうする?莞爾の身になると恐ろしい一冊
泣く子も黙る関東軍の参謀を務め、満州事変の首謀者でもある石原莞爾。実は彼は、女心をくすぐる手紙の達人でもあった。
今日は、彼がドイツ留学中に愛する妻、銻子夫人(愛称:テイちゃん)に宛てた手紙をもとに、彼のラブレター術を検証していきたいと思う。なお、読みやすさを考慮し、文中のカタカナはひらがなに書き換えている。
タイトル:石原莞爾のヨーロッパ体験
著者:伊藤 嘉啓
出版社:芙蓉書房出版
出版日:2009年6月1日
ページ数:226ページ
莞爾流ラブレター術
妻を最優先することを宣言
世の中には、親離れができず結婚後も妻をないがしろにする夫が存在する。その点、石原はきちんと「現代は親より妻の大事な時代」と最愛のテイちゃんに宣言している。両親には一通も出さない徹底ぶりである。
現代は親より妻の大事な時代。小生も此新時代の新人たる資格を失わざらんが為、手紙はこれからも凡て我最愛なる銻子君に宛てることにします。老人がやいても止むを得ない。
はやりものに流されない自分をアピール
いくら外国に行くからといって、場の雰囲気に流され西洋かぶれのダンスをするのは愚の骨頂である。(ちなみにテイちゃんはバイオリンを習っているが、それはそれ、これはこれ。)
男気のある日本男児・石原は、心の中でモヤモヤを溜め込むようなことはしない。その場で「盛に野次り毒付」き、盆踊りを「発議」する。
提案はあえなく却下されるが、実は本人も盆踊りが踊れなかったので結果オーライである。
数日前より西洋人共盛におどる。・・・・・・日本婦人にして彼等にいどまれておどりしものありしに付、盛に野次り毒づく。此の如きダンスより盆踊りの方が数等上等につき、盆踊りを初めんと発議せしも一同やる勇気なく、小生は踊りを知らず残念なり。将来洋行するものは必ず盆おどりくらいは稽古し来るを要す。
子ども好きをアピール
子ども好きな男性は無条件でポイントアップだ。もちろん子どもたちを遊びに連れて行く時は親への挨拶も忘れてはいけない。
子供共の満足たとえるものなく、一番末の子(十才位?)別れる時に日く「母さんにお会いになる時は私共がよく大尉殿の言い付けを守って仲よく(其実時々けんかして泣かされたり)したと言ってください。そうしなければ次から舟遊びに行くことを許されませんから」という。可愛いいものにあらずや。
細やかな気遣い、さりげなく褒める
女性に対して「綺麗に写っている写真が見たいな😍」と言えば、かなりの確率で「普段の私は綺麗じゃないってこと!?怒」と返されるはずだ。石原はその点、「もちろん実物もとっても美しいのですが…何卒!」と前置きをすることを忘れない。こうした気遣いが大切なのだ。
銻子一人の写真へ………………出来るだけ美人らしく(現物も勿論申し分なき美人なるも、いやが上にもよくなる様に)例の壇上で写すこと。
報われない時もある
自分はこんなにマメに連絡をしているのに、一向に返事が来ない…そんな時もあるだろう。そういう時は「手紙がこなすぎてみんなに笑われているんだよう…」と、さりげなく周囲の状況を伝えることで相手にプレッシャーをかけよう。
武官室に居るある人は、駐在員に来る妻君の手紙の数を、亭主思いのバロメーターにしていて、宴会の席毎に笑い草に其点数等発表されます。
そして、返事が来たら大袈裟に喜ぶ。これも大切だ。
先ず一安心せり・・・・・・とにかく先ず先ず安心せり。・・・・・・とにかく心配した。・・・・・・心配をした。可なりの心配をした。
ここから普通の書評
本を手に取ったとき、ページ数や文字サイズ、文体を見れば、自分がその本をどのくらいで読み終えられそうかが分かる、これは読書好きあるあるではないだろうか。この本は分厚いけど文字が大きいから3日くらいで読めるかなとか、文字が小さい上に文章が難解だから2週間はかかりそうだとか、なんとなく予測ができる。
この本も同様なはずだった。最初にぱらぱらとめくった時、この分量なら1日〜2日で読めそうだなと思った。しかし、実際には読み終えるまでに結構な時間がかかってしまった気がする。
理由はたったひとつ。内容が小っ恥ずかしかったからである。
石原莞爾は大正12年(1922年)から約2年半、ドイツに公費留学をしていた。この本は、石原が妻に宛てた手紙をもとに、当時のヨーロッパの状況や石原の内面を探るというコンセプトになっている。
当時のドイツは、第一次世界大戦の敗戦により貧困にあえいでいた。実際、石原の手紙にも、物資不足で列をなす人々や、乱高下する物価の様子などが生々しく描写されている。だが、何より目を引くのは、苛烈な印象の強い「あの」石原莞爾が愛妻に宛てた私信の数々である。
石原は日蓮主義に傾倒していたこともあり、実際に夫人に送られた手紙の内容には宗教的なものも多かった。だが、本書ではそういった面は極力最低限に抑えて、人間味のある部分を抜粋している印象がある。
ドイツまでの旅路でも、エジプトでピラミッドを見たり、パリでオペラを見て楽しむ様子が生き生きと描かれている。同時に、犬の狆に似ている下宿先のドイツ人女性に「ちん君」というあだ名をつけたり、ふくよかな娘を「豚姫」と呼んだりなど、後世に語り継がれる毒舌の片鱗も見え隠れしている。
ちなみに石原は部下には厳しく、よくビンタを喰らわせていたらしい。書評と称してふざけたことを書いてしまったが、私としては今夜彼が夢枕に立たないことを祈るばかりである。