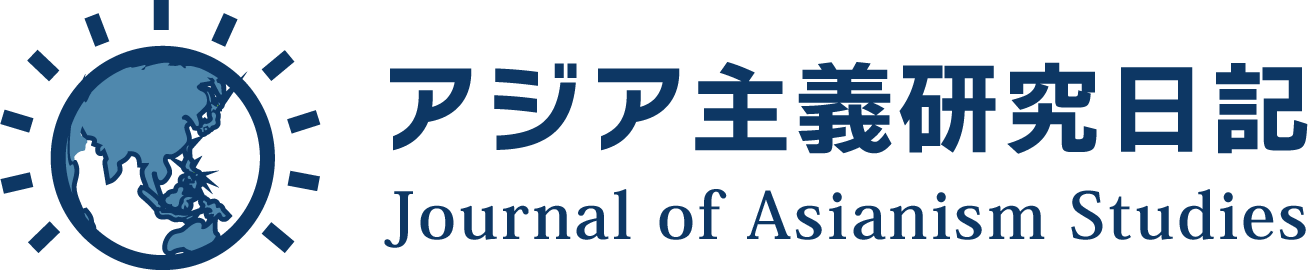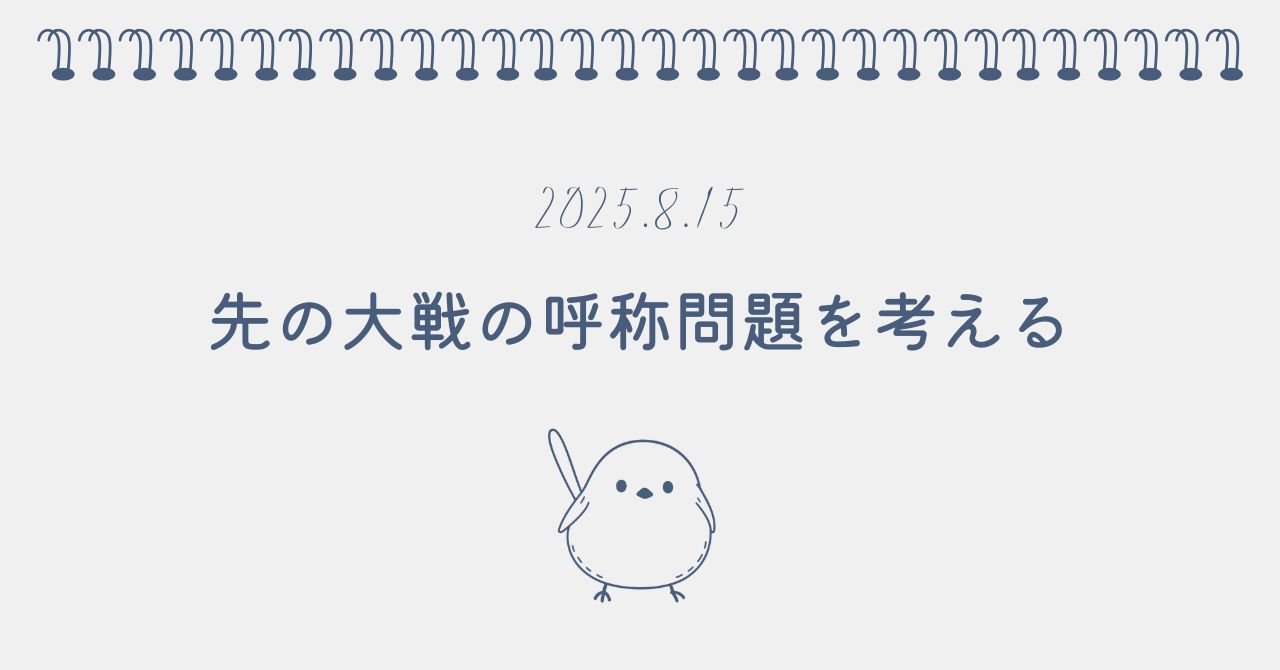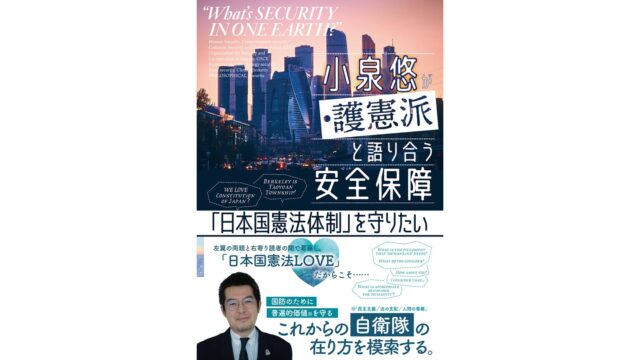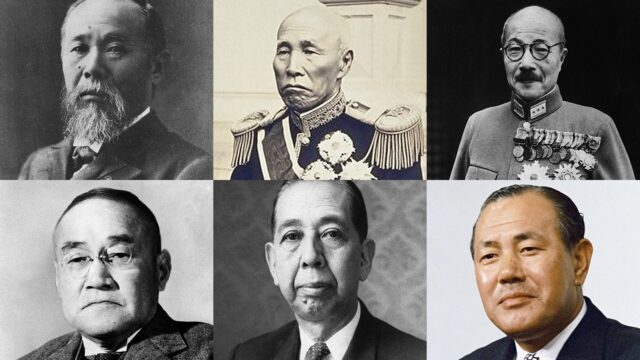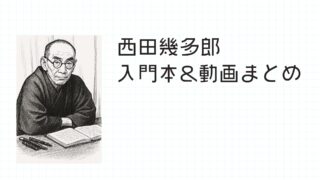今年は、終戦80年目の年にあたる。この時期になると毎回話題になるのが、1945年に終結した戦争をなんと呼ぶのかという問題だ。
第2次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争、さきの大戦…最近では「アジア・太平洋戦争」という言葉を採用している教科書(東京書籍の世界史探究など)もあり、TV等でこの呼び名を聞く機会も増えてきた。
大東亜戦争という呼称を使うことによる批判はしばしば目にする。昨年の4月には自衛隊がSNSでこの呼び名を用いたことが物議を醸し、投稿削除、釈明に追い込まれた。(陸自部隊の「大東亜戦争」投稿を削除 防衛省「誤解を招いた」| 朝日新聞デジタル)
では、そんなに「大東亜戦争」という呼び名はいけないのだろうか。そう思って色々と調べていた際に、1つの論文が目に止まった。以下、防衛省防衛研究所で戦史研究をされている庄司潤一郎氏が書かれた論文を要約して紹介したいと思う。なお、全文はこちらで公開されている:日本における戦争呼称に関する問題の一考察
庄司氏の論文内では、「大東亜戦争」という呼称は、1941年12月10日、大本営政府連絡会議において正式に決定され、対米英戦争および今後発生する可能性のある戦争(支那事変を含む)を一括して指すために採用されたものであると紹介されている。
しかしこの呼称は、戦後すぐに公的な場から姿を消すことになる。1945年12月15日、GHQ(連合国軍総司令部)が発した「神道指令」により、「大東亜戦争」や「八紘一宇」といった用語は、国家神道・軍国主義・超国家主義と深く結びついたものとされ、公文書や公教育の場において使用が禁止されたからだ。その結果、学校教育や政府機関では「大東亜戦争」の使用が中止され、検閲の影響もあり新聞や出版物では代わって「太平洋戦争」という呼称が広く使われるようになっていった。
庄司氏によれば、「太平洋戦争」という呼称は戦後GHQの情報政策により普及したものの、日中戦争を含む戦争全体の実態を的確に表すものではなく、中国戦線の存在を捨象してしまうという問題を抱えているという。加えて、この名称は中南米の戦争と重複する国際的な曖昧さも孕み、戦争の範囲や性格について誤解を生むおそれがあるとし、こうした点を踏まえたうえで、イデオロギー的な意味づけを排除した中立的な立場から、「大東亜戦争」または「アジア・太平洋戦争」といった呼称の再検討を提案している。
要約ここまで。つまり、元々は大東亜戦争だったものがGHQによって呼称変更を余儀なくされ、占領政策が終わった後も定着して今に至るというわけである。この背景を知ってか知らずか、いまだに国内外で論争が起こるというのは何とも根が深い。
庄司氏は、イデオロギー性を排除した上で大東亜戦争ないしはアジア・太平洋戦争という呼び名を提案しているが、実際なんらかの思想を持って大東亜戦争という呼称を用いる人はいるのだろう。そして私は、その時代を生きた人たちが「大東亜戦争」を戦い、生きてきたという歴史がある以上それに賛成である。
もっとも、私が子どもの頃(約20年前…)は、太平洋戦争と習ったし、一般的に馴染みが深いのはこの名前だろう。なので、歴史に興味がない友人や家族との会話であえて「大東亜戦争はさぁ…」と言おうとは思わない。それはプライベートで「資料をお送りしますのでご査収ください」などと言わないのとほぼ同じ理由である。
もうひとつ。先の大戦(さきの大戦)という呼称がある。天皇陛下のおことばや日本政府の公式文章で使われている呼称だ。これに対してもさまざまな意見があるが、この言葉が使えるのは終戦から80年、新たな大戦が起こらず日本が平和だったからでもあり、そう考えると悪くない呼び方に思える。終戦の日の今日、戦争で命を落とされた方に哀悼の誠を捧げるとともに、この先もずっと平和が続くように祈りたい。
追記:呼称問題に対する庄司先生の考え方については、下記の動画でも紹介されている。わかりやすいのでこちらぜひ。